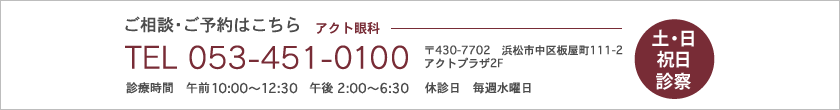| どうして近視になるの? | |
| 近視の原因については解明されておりませんが、一般的に近くを見ることが多いという環境が、遠くが見えにくい近視の発生や進行の原因として考えられています。遺伝によるものも原因という説もあります。 また10代の成長期において、眼軸(眼球の大きさ)が伸び、その為に近視が進むこともあり、その場合は体の成長と同じで防ぎようがない場合もあります。また、使っているコンタクトレンズや眼鏡が見えにくいままでいることも負担になり、近視が進む原因になることもあります。 視力の変化においては、個人差があるため、ゲームなどに熱中しても近視になる子とならない子がいるので、目を使いすぎると必ずしも近視になるとは限りませんが、これらのことを踏まえて、日頃から目に負担のかかりにくい環境を作ることが近視の予防には非常に大切なことです。 |
| 仮性近視って何? | |
| 近くばかりを長く見続けると、目の中の水晶体(レンズ)の厚さを「調節」している毛様体といわれるものが異常に緊張して、一時的に近視の状態になってしまいます。これを俗に「仮性近視」と呼ばれていますが、「調節緊張症」という病名がついており、調節をマヒさせる(毛様体を休ませる)点眼薬をつけて治療します。効果が出ない場合はコンタクトレンズや眼鏡といった矯正が必要となります。 |
| 一度コンタクトレンズや眼鏡を使うと、度がすすむの? | |
| コンタクトレンズや眼鏡を使うことが原因で、度がすすむことはありません。視力の変化については個人差がありますが、身長が伸びるように成長とともにある程度は進行する場合もあります。度が進むからといって見えにくい眼鏡をかけている方もいますが、生活に支障があると、かえって度がすすむ原因になることもあります。正しい視力をだしてあげることが重要なことと言えます。 |
| VDT症候群って何? | |
| VDTは、「Visual
Display Terminals」の略語で、パソコン・テレビゲームの長時間の使用により、目や体や心に影響のでる病気で、別名テクノストレス眼症(がんしょう)とも呼ばれています。 オフィスでの長時間のデスクワークでは、視線はディスプレイ、キーボード、資料の間を絶えず行き来するため、疲労が起こりやすく、目の痛みや充血、かすみなどの症状が現われます。また、長時間ディスプレイを凝視している際、意識してまばたきをしていないと、通常の4分の1の回数に減ることでドライアイの原因になることもあります。 予防法としては、適度な休憩(少なくとも1時間に10〜15分程は、目を休ませること)や、体の緊張をほぐす為の体操、目薬などが有効です。もちろん、作業に適したコンタクトレンズや眼鏡を使用することも大切です。眼精疲労が長期にわたることで症状が悪化する事もありますので、無理をせず受診することをおすすめ致します。 |
| 花粉症って? | |
| 花粉症とは、スギやヒノキなどの植物の花粉が原因となって、くしゃみ・鼻みず・目のかゆみなどのアレルギー症状を起こす病気です。 本来、人間は外部からの異物が鼻のなかに吸い込まれると、アレルギーを起こす物質である抗原(アレルゲン)が溶け出し、この抗原と闘うために人間は体内で抗体を作り出すのです。抗体は、抗原を捕まえるときにヒスタミンなどいくつかの物質を放出するので、これが神経を刺激して炎症を起こしてしまうのです。外部の異物に対する体の防衛反応が過剰になることで、花粉などの異物にも反応が強くなり、結果として花粉症になるのです。 |
| どんな人が花粉症にかかりやすいの? | |
| 花粉症は、今や国民病とまで言われる程多くの患者がおり、年々増加傾向にあります。遺伝的要素と環境による要素が原因といわれていますが、一般的に、花粉症になりやすい人を以下にまとめました。 ・ アレルギー体質の傾向の強い人(遺伝も含む) ・ インスタント食品などによる食生活の乱れ ・ 都市部などの自動車の排気ガスが多い環境 花粉症はコップに水の溢れるように、ある日突然発症します。コップの水が溢れる直前までは自覚症状がまったくないので、以上の条件に心当たりのある人は、花粉症を発症しないための自己管理をしっかりとしましょう。また、花粉症の方は、症状が悪化しないよう早期対応が大切です。目がかゆくなるなどの症状が出る前に受診しましょう。 |
| 花粉症対策を教えて | |
| 簡単に出来て、効果があるのはマスクをすることです。マスクの下に軽く湿らせた綿や布を1枚重ねるとさらに効果があります。また、目に入る花粉を防ぐ為の専用の眼鏡も有効です。 また、外出先から帰宅する際には必ず服についた花粉をしっかり払うこと、洗濯物や布団を外に干さないこと、花粉症の時期は掃除機ではなく濡れた雑巾を使うこと、など身近なところからの対策が必要です。 また花粉症の時期は、なるべく眼鏡の使用が好ましいですが、コンタクトレンズが必要な場合は1日使いすてレンズにするなどもよいでしょう。 |